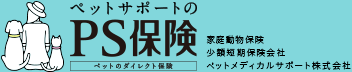猫のホルモン性脱毛症の症状と原因、治療法について
猫のホルモン性脱毛症ってどんな病気?
ホルモン性脱毛症は、ホルモン分泌の異常によって、体の各所に脱毛が起きてしまう病気です。
猫にホルモン性脱毛症の症状が見受けられる場合には、原因となる疾患の治療が必要です。
どうして症状が出るの? 原因は?
猫のホルモン性脱毛症の原因として、下記のような異常が考えられています。
副腎皮質ホルモンの異常
副腎皮質ホルモンの過剰分泌はクッシング症候群が原因とされ、クッシング症候群の原因は、遺伝、脳内の腫瘍、副腎の腫瘍などです。
性ホルモンの異常
猫の性ホルモン異常の原因は、先天的なものとして「卵巣の異常(I型・II型)が、最も多いと言われています。
I型はエストロゲンの不足が原因で、II型は逆にエストロゲンが過剰分泌されることが原因です。
後天的な原因としては、猫の精巣腫瘍や避妊・去勢手術によるホルモンバランスの崩れなどが挙げられます。
甲状腺ホルモンの異常
甲状腺機能低下症によって甲状腺ホルモンの異常が見られます。猫の甲状腺機能低下症の原因は、自己免疫疾患や甲状腺の萎縮と考えられていますが、クッシング症候群の影響もあると言われています。
成長ホルモンの異常
猫の成長ホルモン異常の原因は、生まれつき成長ホルモンを分泌する下垂体に異常のある先天的「下垂体矮小症」が最も多いと言われています。
これは猫の場合、ほとんどないと言われていますが、犬ではまれに発症します。
後天的なものの場合は、ほとんどが原因不明です。
どんな猫がホルモン性脱毛症にかかりやすいの?
品種問わず、子猫時期になりやすいと言われています。
猫のホルモン性脱毛症の症状とチェック項目
ホルモン性の脱毛症の特徴として、「脱毛部分が左右対称性」であることが挙げられます。
また、原因となるホルモンの分泌異常によって、脱毛の部位や症状が異なります。
副腎皮質ホルモンの異常
副腎皮質ホルモンが過剰に分泌される(クッシング症候群)と、猫の腹部や耳の先端の毛が抜けていきます。
また、多飲多尿や腹部が腫れるなどの症状や糖尿病を引き超すこともあります。
性ホルモンの異常
雌猫のエストロゲンという性ホルモンが過剰に分泌されると、生殖器や肛門周りに脱毛の症状が出ます。
性ホルモン異常による脱毛症は、脱毛以外にも発情期が乱れたり、繁殖力が低下したりなどの症状も出ます。
また、去勢した雄猫の場合は、テストステロンの減少に伴い、お尻、尻尾の付け根、横腹に、脱毛がゆっくりとした進行で見られることもあります。
甲状腺ホルモンの異常
甲状腺機能低下症に伴い、甲状腺ホルモンに異常を来し、まれに脱毛の症状が出る場合があります。
甲状腺機能低下症のより詳しい原因、症状、予防については獣医師監修の「猫の甲状腺機能低下症」を併せてご覧ください。
左右対称性の脱毛が見受けられるほか、色素沈着の症状が出ることもあります。
成長ホルモンの異常
成長ホルモンが不足すると、猫の首・体幹・太ももの裏側などに、左右対称性の脱毛や色素沈着、皮膚の弱化などの症状が出ます。
多くは生後2~3ヶ月で発症しますが、後天的に発症するケースもあります。
ただし、成長ホルモンの異常に伴う脱毛症は、猫ではまれです。
どうやって予防したらいいの?
猫に脱毛の症状が見られた場合は、かゆがっていなくてもかかりつけ医と相談しておきましょう。
また、普段から猫の体のチェック(脱毛や脱毛の範囲。皮膚の色。赤みや発疹など)をしてください。
少しでも気になることがあったら、速やかに獣医師の診察を受けましょう。
猫のホルモン性脱毛症に見られる症状の関連記事
猫の皮膚・アレルギーの病気
猫種別の保険料
当社のペット保険は、猫種による保険料の違いがありません。
また、「ペット保険取扱の猫種分類表」に契約実績のある猫種をまとめていますが、未記載の猫種であっても保険料は同じです。
あ行に属する猫の種類
- アビシニアン
- アメリカンカール
- アメリカンキューダ
- アメリカンショートヘア
- アメリカンボブテイル
- アメリカンポリダクティル
- アメリカンワイヤーヘア
- アメリカンリングテイル
- アラビアンマウ
- アルパインリンクス
- イジアン
- ウラルレックス
- エイジアン
- エキゾチックショートヘア
- エジプシャン・マウ
- オイイーボブ
- オーストラリアンミスト
- オシキャット
- オホサスレス
- オリエンタル
- オリエンタルバイカラー
か行に属する猫の種類
- カラーポイントショートヘア
- カリフォルニアスパングルド
- キプロスアフロディーテ
- キムリック
- キンカロー
- クリッパーキャット
- クリリアンボブテイル
- コーニッシュレックス
- コラット
さ行に属する猫の種類
- サイベリアン
- サバンナ
- サファリ
- ジャパニーズボブテイル
- ジャーマンレックス
- シャム
- シャルトリュー
- シャンティリー
- ジェネッタ
- シンガプーラ
- スキフトイボブテイル
- スクーカム
- スコティッシュフォールド
- スノーシュー
- スフィンクス
- セイシェルワ
- セイロンキャット
- セルカークレックス
- セレンゲティ
- ソコケ
- ソマリ
た行に属する猫の種類
- ターキッシュアンゴラ
- ターキッシュ・バン
- チートー
- チャウシー
- デザートリンクス
- テネシーレックス
- デボンレックス
- トイガー
- ドウェルフ
- ドラゴンリー
- トンキニーズ
- ドンスコイ
な行に属する猫の種類
- ナポレオン
- ネベロング
- ノルウェージャンフォレストキャット
は行に属する猫の種類
- バーマン
- バーミーズ
- バーレイニディルムンキャット
- ハイランドリンクス
- ハバナブラウン
- ハバリ
- バリニーズ
- バンビーノ
- ピーターボールド
- ピクシーボブ
- ヒマラヤン
- フォールデックス
- ブラジリアンショートヘアー
- ブランブル
- ブリティッシュショートヘア
- ブリティッシュロングヘアー
- ペルシャ
- ベンガル
- ボンベイ
ま行に属する猫の種類
や行に属する猫の種類
- ユークレイニアンレフコイ
- ヨークチョコレート
- ヨーロピアンショートヘア
ら行に属する猫の種類

-
記事監修:ペットメディカルサポート株式会社
動物病院での実務経験をもつベテラン獣医師および動物看護師が多数在籍するペット保険の少額短期保険会社。スタッフ全員が動物好きなのはもちろんのこと、犬や猫といったペットを飼っている者も多いので、飼い主様と同じ目線に立ったサポートに取り組んでいます。
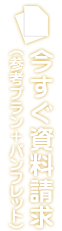


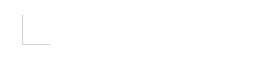
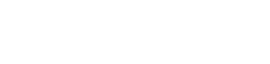

![新規お客さまご相談窓口/資料請求受付:0120-535-797 [受付時間]平日8:00〜19:30 土曜9:00〜18:00(日・祝日・年末年始を除く)](/uploads/2023/03/27/tel01_sp.png?date=202303271629)