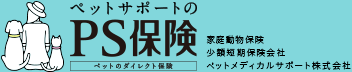ペット保険の免責とは?免責事由・免責金額・免責期間(待機期間)について解説
「ペット保険に入っていれば安心」と思っていても、いざ保険金を請求すると「この場合は補償の対象外です」と言われてしまうことがあります。その理由の1つが「免責」です。
「免責」とは文字どおり「責任を免れる」という意味で、保険会社が補償の対象としない条件や範囲をあらかじめ定めているものを指します。
ペット保険にはいくつかの免責があり、理解していないと「想定外の自己負担」が発生する可能性があります。
免責には大きく分けて以下の3種類があります。
- 免責事由:補償対象外となるケースや条件
- 免責金額:自己負担が発生する金額
- 免責期間(待機期間)※:契約直後に補償が適用されない期間 ※保険分野全体では「免責期間」と「待機期間」を区別して用いるのが一般的ですが、ペット保険の説明においては「契約直後に補償が始まらない期間(待機期間)」を「免責期間」として説明するケースがあります。この記事ではその整理に基づいています。
この記事では、この3つの免責を具体的に解説していきます。
ペット保険の「免責事由」について
ペット保険における免責事由とは、保険会社が補償の対象としないケースや条件を示すものです。
これは「保険金を支払わない条件」とも言え、保険契約の基本的な仕組みとして幅広く使われている考え方です。
もし免責事由を理解していないと、実際に請求しようとしたときに「この場合は補償できません」と説明を受けて驚くこともあります。
加入する際には、どのような条件が免責事由に該当するかを確認しておくと、後々のトラブルを防ぎやすくなります。
また、免責事由の内容は保険会社やプランによって異なるため、契約前に比較しておくことが安心につながります。
ペット保険の「免責事由」となる条件
保険会社によって免責事由は異なりますが、ここではペット保険「PS保険」の場合の免責事由を紹介します。
補償開始前(保険始期日より前)に発生していたケガや病気
補償開始前(保険始期日より前)にすでに発症していたケガや病気については、補償の対象になりません。加入前から続いている治療や、それに関連する病気の治療費も含まれます。
「過去にさかのぼって補償されるわけではない」という点を押さえておきましょう。
遺伝性疾患や先天性異常
股関節形成不全などの遺伝性の病気は補償の対象外です。
また、補償開始前(保険始期日より前)にすでに見つかっていた先天性異常については、補償開始前(保険始期日より前)に見つかっていた場合は補償されません。
契約後に確認された場合の取扱いは保険会社やプランにより異なるため、事前にご確認ください。
ワクチンなどで予防できる病気
ワクチン接種で防げる病気は、基本的に補償の対象外です。ただし、ワクチンの有効期間内に発症した場合補償されます。
日常の予防ケアと保険の役割が分かれていると理解していただくと安心です。
予防に関する費用
健康維持を目的とした診療やワクチン接種の費用は、補償の対象外です。ワクチンによるアレルギー対応や、病気を予防するための検査や投薬も含まれます。
こちらは「治療」ではなく「予防」にあたるため、自己負担となります。
ケガや病気にあたらないもの
正常な妊娠・出産、帝王切開(母体救命措置を除く)、避妊・去勢手術などは補償されません。さらに、肛門腺除去や肛門嚢絞り、爪切り、歯石取りなども対象外です。
美容を目的とした手術や、病気予防のための注射・薬の費用も含まれます。
「健康管理や生活のための処置」と「病気やケガの治療」は分けて考えることがポイントです。
健康診断や代替医療
定期的な健康診断や、漢方・針灸・温泉療法・酸素療法などの代替療法も対象外です。
これらは「安心のためのチェック」や「補助的なケア」と位置づけられるため、自己負担になります。
診療(診察または治療)にあたらない費用
療法食やサプリメント、ビタミン剤などの健康食品は補償の対象外です。
また、シャンプー代や入浴費用、イヤークリーナー費用なども対象外となります。ペットホテルの利用費や移送費、診断書の作成費用も含まれます。
治療そのものではなく「周辺的な費用」にあたるものは、自己負担になると覚えておくと安心です。
上記以外の免責事由に関しては「重要事項説明書」をご確認ください。
ペット保険の「免責金額」について
免責金額とは、保険金を請求するときに飼い主さまが自己負担することになる一定の金額を指します。
この金額を差し引いた残額に対して、補償割合が適用される仕組みです。
たとえば、免責金額が1万円に設定されている場合、1万円までは自己負担となり、それを超えた部分から保険金の対象となります。
加入前にしっかり理解しておくことで、思わぬ負担感を避けられます。
免責金額があるペット保険のメリット
免責金額があることで、保険料を抑えられるというメリットがあります。
ちょっとした通院や軽い治療費は自己負担になりますが、その分、毎月の保険料をお手ごろにできるのです。
大きなケガや手術など、高額な医療費がかかる場面ではしっかり補償を受けられるため、「いざというときの安心」を得られます。
ペットの健康状態が比較的安定していて、日常的に大きな治療費がかからない子にとっては、無理のない選択肢になることもあるでしょう。
免責金額があるペット保険のデメリット
少額の診療費では保険が使えず、結果的に「思ったより自己負担が多い」と感じる場面があるかもしれません。
特に、通院が増えやすい子や、慢性的なケアが必要な子にとっては、毎回の負担が積み重なることがあります。
また、免責金額の設定方法や計算方法は保険会社によって異なるため、分かりにくさを感じる場合もあります。
「どのくらいの治療費から保険が使えるのか」をしっかり確認しておかないと、加入後にギャップを感じる原因になってしまうこともあります。
参考:ペット保険の免責金額についてペット保険の「免責期間(待機期間)」について
免責期間(待機期間)とは、契約をしてから一定期間は補償が適用されない仕組みを指します。
契約日からすぐに補償が始まるのではなく、あらかじめ定められた待機期間を経てから補償が有効となります。
この制度は、加入前に症状があった病気や、契約直後に発症したケースを公平に扱うために設けられています。
一般的に、ケガと病気では免責期間(待機期間)が異なることが多く、ケガは短く、病気はやや長めに設定される傾向があります。
また、病気の種類によっては通常より長めの免責期間(待機期間)を設ける場合もあります。
参考:ペット保険の免責期間について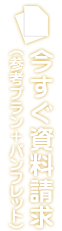


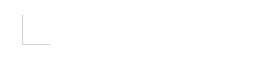
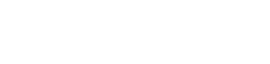

![新規お客さまご相談窓口/資料請求受付:0120-535-797 [受付時間]平日8:00〜19:30 土曜9:00〜18:00(日・祝日・年末年始を除く)](/uploads/2023/03/27/tel01_sp.png?date=202303271629)