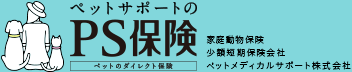ペット保険の不正請求(いわゆる保険金詐欺)とは?
ペット保険は、ペットの病気・けがの治療費を補償する保険です。しかし、一部では不正に保険金を受け取ろうとする行為が問題となっています。
この行為は保険会社では「不正請求」と呼ばれますが、一般的には「保険金詐欺」と表現されることもあります。
この記事では、不正とみなされる代表的なケースを紹介しながら、ペット保険を正しく安心して利用するための注意点を解説します。
ペット保険の不正請求(いわゆる保険金詐欺)で見られる主なケース
ペット保険の不正請求には、以下のようなものが存在します。
- 虚偽の診療や治療を申告する
- 実際の金額より高い費用を請求する
- 他人のペットを自分のペットと偽る
- 領収書や診療明細書を改ざんする
それぞれ詳しく解説していきます。
虚偽の診療や治療を申告する
実際には受けていない診療や治療を受けたように装って請求する行為です。
例えば、動物病院に通院していないのに診療を受けたと報告したり、存在しない処置を申告したりするケースがこれにあたります。
このような行為は一見すると小さな嘘に見えるかもしれませんが、保険金を不正に得ることになるため重大な不正請求です。
発覚した場合は、契約解除や返還義務にとどまらず、刑事責任を問われる可能性があります。
実際の金額より高い費用を請求する
本来の治療費より高額に水増しして申告するケースです。
例えば、実際の治療費が5,000円だったにもかかわらず、領収書を加工して1万円と記載し、差額をだまし取るような行為が該当します。
少額であっても不正請求として扱われ、刑事事件に発展する可能性もあります。
他人のペットを自分のペットと偽る
契約対象外の動物を自分の契約で補償されるように装って請求する行為です。
例えば、友人や親族の犬や猫の治療費を、自分が加入しているペット保険で請求するといったケースが挙げられます。
このような行為は意図的な虚偽申告であり、明確に不正請求と見なされます。
ペットの個体識別情報(マイクロチップや診療履歴)が整備されつつある現在では、こうした不正は発覚しやすく、悪質と判断されれば刑事責任を問われる可能性も高まります。
領収書や診療明細書を改ざんする
診療明細書や領収書を書き換えたり、治療項目を追加したりする行為です。
例えば、実際に受けていない検査を「実施した」として記載を加えたり、金額欄を修正して高額に見せかけたりするケースがこれにあたります。
こうした改ざんは書類を用いた明確な虚偽申告であり、発覚すれば保険契約の解除や返還義務だけでなく、刑事責任に直結する重大な行為です。
保険会社は請求内容に不自然さがある場合、病院への照会や専門調査員による調査を行うため、発覚するリスクは極めて高いといえます。
ペット保険を正しく利用するために
ペット保険は、飼い主の皆さまと大切なご家族であるペットを医療費の負担から守るための保険です。
一方で、誤った利用や不正な請求は、契約の解除や返還義務につながるだけでなく、場合によっては大きなトラブルに発展することもあります。
安心してペット保険をご利用いただくために、次の点にご注意ください。
- 架空の診療や水増し請求など、不正とみなされる行為は行わないこと
- ご加入の保険契約内容をよく確認し、補償の対象や条件を正しく理解すること
- 診療明細書や領収書は正しい内容で保管し、改ざんしないこと
- ご不明な点や不安があれば、必ず保険会社へご相談いただくこと
ペット保険を正しく利用することが、すべての契約者さまに安心をお届けすることにつながります。
-

- 記事監修:ペットメディカルサポート株式会社 動物病院での実務経験をもつベテラン獣医師および動物看護師が多数在籍するペット保険の少額短期保険会社。スタッフ全員が動物好きなのはもちろんのこと、犬や猫といったペットを飼っている者も多いので、飼い主様と同じ目線に立ったサポートに取り組んでいます。
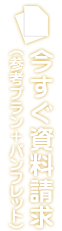


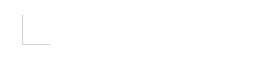
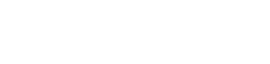

![新規お客さまご相談窓口/資料請求受付:0120-535-797 [受付時間]平日8:00〜19:30 土曜9:00〜18:00(日・祝日・年末年始を除く)](/uploads/2023/03/27/tel01_sp.png?date=202303271629)