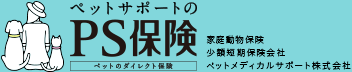保護犬・保護猫(元野良猫)でもペット保険に加入できる?加入の流れや注意点を解説
新しく家族に迎えた保護犬や保護猫、あるいは野良猫を保護して飼い始めた場合、健康状態に不安を感じる飼い主さまも少なくありません。
特に、過去の医療履歴が分からないケースでは、万が一のケガや病気に備えて、ペット保険の加入を検討される方が多いようです。
この記事では、保護犬や保護猫を家族に迎えた方に向けて、ペット保険に加入できるかどうか、また加入の流れや注意点について詳しく解説します。
保護犬・保護猫でもペット保険に加入できる?
保護犬・保護猫も、基本的にはペットショップやブリーダーから迎えたペットと同様に、条件を満たせばペット保険に加入できます。
生年月日が分からない場合はどうする?
まずは動物病院を受診して、獣医師にペットの推定年齢を確認してもらいましょう。ペット保険は年齢による加入制限があるため、推定年齢を正確に伝える必要があります。
保護犬・保護猫がペット保険に加入する際の注意点
健康状態によっては加入できないこともある
ペット保険に申し込むときは、ペットの健康状態の告知が必要です。
保険会社はこの情報をもとに審査を行うため、加入条件を満たさない場合にはご加入いただけないことがあります。
加入を検討する際は、各保険会社が用意している重要事項説明書をもとに、条件をしっかり確認しておきましょう。
参照:https://pshoken.co.jp/comparison/disclosure.html
年齢制限に注意
ペット保険は一般的に、新規加入できる年齢に制限が設けられています。
たとえばPS保険では、補償開始日時点で生後30日以上から8歳11か月までがご加入いただけます。
特に高齢のペットを保護した場合は、この年齢制限によって加入できない可能性があるため注意が必要です。
参照:https://pshoken.co.jp/comparison/comp_age.html
ペット保険加入の流れ
保護犬・保護猫がペット保険に入るまでの流れは、以下のようになります。
動物病院を受診する
まず、動物病院でペットの健康診断を受けましょう。
このときに獣医師に推定年齢を判断してもらい、健康状態を確認しておくことが大切です。
保険の申し込みには、これらの正確な情報が必要になります。
最適な保険のプランを選ぶ
ペット保険会社によって、補償内容や保険料は異なります。
たとえば「通院・入院・手術のどれが対象になるのか」「治療費の何割まで補償されるのか」などがプランごとに異なります。契約前には、必ず各社が用意している重要事項説明書を確認しましょう。
申し込み
病院で確認した推定年齢や健康状態を正しく告知して、保険の申し込みを行います。
虚偽の告知をすると契約が無効になることもあるため、必ず正しい情報を伝えることが大切です。
加入審査
申し込み後は保険会社が審査を行い、告知された内容をもとに加入できるかどうかを判断します。
加入完了・補償開始
審査に通過すると契約が成立し、補償が始まります。
申し込み日と補償開始日は必ずしも同じではありません。補償開始日については、各保険会社の重要事項説明書を確認しておくと安心です。
-

- 記事監修:ペットメディカルサポート株式会社 動物病院での実務経験をもつベテラン獣医師および動物看護師が多数在籍するペット保険の少額短期保険会社。スタッフ全員が動物好きなのはもちろんのこと、犬や猫といったペットを飼っている者も多いので、飼い主様と同じ目線に立ったサポートに取り組んでいます。
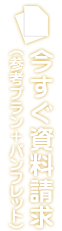


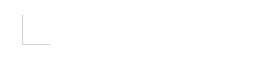
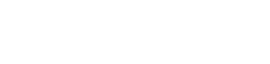

![新規お客さまご相談窓口/資料請求受付:0120-535-797 [受付時間]平日8:00〜19:30 土曜9:00〜18:00(日・祝日・年末年始を除く)](/uploads/2023/03/27/tel01_sp.png?date=202303271629)